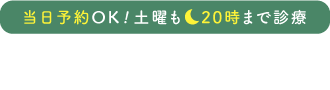九段下駅前歯科クリニックによく頂く丸尾の質問をまとめました
丸尾
- 気になる口臭の治療は、どういったものがありますか?
-

Dr.丸尾
口臭の原因がお口の中の病気(主に歯周病)という場合は、しっかりとした歯周病の治療が必要だったり、正しい歯ブラシの当て方、ケアのタイミング、ケアの仕方など、詳しく・細かく伝えるべきことがたくさんあります。
一度、歯医者さんで歯周病の検査をされてから治療を行われることをお勧めします。 - インプラントは、ずっと使い続けることができますか?
-

Dr.丸尾
基本的には使い続けられます。
ただ、使っていく中で被せ物(人工歯)が壊れたり、インプラントが埋まっている歯ぐきが歯周病になる(インプラント周囲炎)こともありますので、正しいセルフケアの実践はもちろん、歯科医院でのメンテナンスをしたりなどの定期的なチェックを必ず受けましょう。 - インプラント治療は何歳から何歳までが対象ですか?
-

Dr.丸尾
明確な年齢制限はありませんが、お子さんの場合は今後の骨や顎の成長に関わってくるので、成長期の子供は避けることをお勧めします。
- 歯周病になっているのですが、インプラントはできますか?
-

Dr.丸尾
今現在、お口の中が歯周病という状態であまりにもコントロールされていない場合だと、せっかくのインプラントも長持ちしづらいです。
インプラント自体は虫歯にはなりませんが、インプラントが埋まっている歯ぐきや骨は歯周病になりますので(インプラント周囲炎)、しっかり口腔環境を改善し、歯周病リスクをコントロールしてから治療を進められることを強くお勧めします。 - インプラントを何本入れればいいのですか?
-

Dr.丸尾
当然それぞれの状態によりますが、歯をたくさん失っているからといって全部の本数分が必要かというと、そうではありません。
大多数の歯を失っていても、少数本のインプラントで、ブリッジや入れ歯状になった複数構成の人工歯を固定させることもできます。
どんな治療計画が適しているか、担当歯科医師と相談の上、決めていきます。 - インプラント治療の期間中、歯がない所はどうしますか?
-

Dr.丸尾
前歯や小臼歯などの見える部分であれば、仮歯のようなものを入れる場合もあります。奥歯の場合、その歯が無いと食べ物が噛めないなどの支障があれば一時的に入れ歯を使ったり、仮歯を使ったりする場合もあります。
インプラントの場所や本数など、ケースバイケースなので、担当の歯科医師と相談していきます。 - インプラント手術の痛みや腫れが心配。。。
-

Dr.丸尾
インプラント手術中は局所麻酔をしていますので、痛みの心配はありません。
手術後に関しても、痛みを感じる方はとても少ないですが、腫れる方は10人に2、3人はいらっしゃいます。
ただ、インプラントを入れた本数によるものであったり、同じ人でも右側は腫れたけど左側は腫れなかったなど、その日の体調に左右されることも大いにあります。 - 金属アレルギーを持っているので、インプラントは不可能?
-

Dr.丸尾
インプラント体(人工歯根部分)を構成するチタンは、比較的金属アレルギーがないと言われている材質です。しかし、上に被せる人工歯が金属の場合は、アレルギーに当てはまる可能性も否定できません。
ただ、金属ではなく、セラミックやジルコニアと言ったメタルフリーの素材を用いた人工歯も作製できるので、基本的には可能です。 - 虫歯予防に効果的なことは?
-

Dr.丸尾
歯磨き(ブラッシング)はとても大事ですので、正しくかつ継続してできているかどうかを定期検診の際に歯科衛生士にチェックしてもらいましょう。検診してメンテナンスしてもらうのが第一です。
歯磨き以外にも、食事や甘い物の摂り方など、日頃の生活習慣のアドバイスも受けると良いでしょう。
その他にホームケアで使える物として、フッ素入りの歯磨き粉や、キシリトール100%のガムやタブレットも予防効果がありお勧めです。 - 定期検診へは、どれくらいの頻度で行くべきですか?
-

Dr.丸尾
最低でも3ヶ月から4ヶ月に一度、というのが一般的ですが、患者様のお口の状態、虫歯・歯周病リスクによって変わります。歯科医師や歯科衛生士の指示のもと、適した受診を行いましょう。